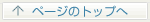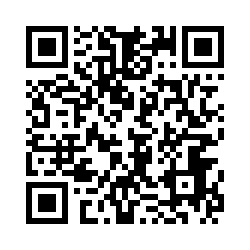【小・中・高】100点を目指しすぎるのは時には問題!?

【小・中・高】100点を目指しすぎるのは時には問題!?
6月ですが、すでに結構暑いですね。
学校によっては5月に体育祭を予定していたものの、コロナの影響で9月に一時的に計画しているところも多いようです。
最近の5月の暑さを考えても、9月実施の方が子どもたちや観客席の保護者からしても良いかもしれません・・・。
さて、今日のテーマは「どこまで目指すかで勉強のペースを変えよう」といった内容です。
本校には、中学生と高校生の塾生がいるのですが、どれくらいのペースで勉強すれば良いのか、迷っているシーンを目にします。
中2・3生であれば、目指す高校に応じてどのレベルまで習熟しておけばよいのかが違います。
高校生であれば、目指す大学ですね。
そもそも、ほとんどのテスト(定期テスト・実力テスト・模試など)は、満点が取りにくいような問題設定になっています。
そう簡単に満点が取れる(難易度が易しすぎる)と差がつかないですし、習熟度が図れないからですね。
ただ、子どもたちは100点満点を取ろうと頑張ります。
これはもちろん良いことですし、頑張るモチベーションに繋げてほしいとも思います。
その上で困ることがあります。
実力テストにしろ、模試にしろ、現段階の実力を調べるものです。
小学校や中学校のテストで良い点を取っていた子ほど、実力テストや模試で点数が取れなった時に引きずります。
「自分はこんなにも学力がついていなかったのか」と。
僕から言えば、今回間違っといてラッキーで良いのです。
本番で同じ問題が出たときに、きちんと解ければよいのです。
では、どこまで習熟しておけばよいのか。
教科書のどのレベル?基本・標準・発展?
これを知るのは難しいかもしれませんね。
塾生には伝えていますが。
それを知る一番簡単な方法が過去問を見ることです。
今の実力から、どこまで力を伸ばせばよいのかが明らかになります。
その指標がないままに、やみくもに『全部の問題を解き切ってやろう』なんて考えはやめてくださいね。
この記事を読んで、勉強のペースについて今一度考えてもらえましたら幸いです。